2007.12.21 ノー・カントリー・フォー・オールドメン



ジョエル&イーサン・コーエン『ノーカントリー』を観てきた。
基本的には、納得。
早めに行ったのが幸したけれど、満員で入れなかった人もいたようだ。
暑い試写室、銃声の効果音が身体のなかにドゥンドゥンとこだまする。

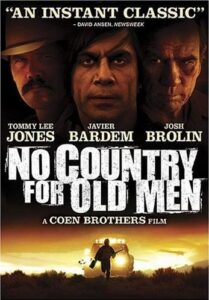
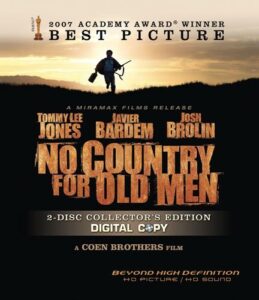
ジェイムズ・グレイディ『狂犬は眠らない』にびっくり。
数あるリストラ・スパイの話でもダントツだ。CIAの秘密精神病院でグループ・セラピーを受けていた「狂人」が脱走する―― というのは、営業用紹介のモードで。
びっくりしたのは、別のこと。献辞を捧げられた名前なのだ。
ボブ・ディラン
ビリー・ホリディ
ブルース・スプリングスティーン
リチャード・トンプスン
ブライアン・ウィルスン
これだけで「同世代の絆」を感じてしまうのは、ただのセンチメントか。ともかく、読まずにはいられなくなる。
たしかに、この小説の底には、ザ・ボスの「ジャングルランド」が執拗に流れている。
その一貫性は、たとえば「ボーン・イン・ザ・USA」がある種のメッセージ・ソングとして利用された例などと比べて、はるかに内在的なのだ。
他に、トンプスンの「アイ・フィール・ソー・グッド」、ザ・ビーチボーイズの「ドント・ウォーリー・ベイビー」は、映画の挿入歌といった使われ方をしている。
ビリー・ホリディの場合は、人物の一人が「エンジェル・オブ・ハーレム」の投影なのだろう。
そして、ディランはどこに?
見当がつくのは、この小説が、マーティン・スコセッシの『ノー・ディレクション・ホーム』に多大な刺激をうけているのだろうということ。
「世代の唄」がとりわけ低声で語られる季節がふたたび巡り来たったような。
2007年問題の先頭を切ってシニアに突入した身として、いっそう強く感じるのだろうか。
『ダイハード4.0』なんかでも、ブルース・ウィリスがクリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルの講釈をして若者に馬鹿にされるシーンがあったりした。
まあ、クリームやレッド・ツェッペリンの復活を目にしてどんな感傷にひたるかは、それぞれの勝手だけれど。
数あるリストラ・スパイの話でもダントツだ。CIAの秘密精神病院でグループ・セラピーを受けていた「狂人」が脱走する―― というのは、営業用紹介のモードで。
びっくりしたのは、別のこと。献辞を捧げられた名前なのだ。
ボブ・ディラン
ビリー・ホリディ
ブルース・スプリングスティーン
リチャード・トンプスン
ブライアン・ウィルスン
これだけで「同世代の絆」を感じてしまうのは、ただのセンチメントか。ともかく、読まずにはいられなくなる。
たしかに、この小説の底には、ザ・ボスの「ジャングルランド」が執拗に流れている。
その一貫性は、たとえば「ボーン・イン・ザ・USA」がある種のメッセージ・ソングとして利用された例などと比べて、はるかに内在的なのだ。
他に、トンプスンの「アイ・フィール・ソー・グッド」、ザ・ビーチボーイズの「ドント・ウォーリー・ベイビー」は、映画の挿入歌といった使われ方をしている。
ビリー・ホリディの場合は、人物の一人が「エンジェル・オブ・ハーレム」の投影なのだろう。
そして、ディランはどこに?
見当がつくのは、この小説が、マーティン・スコセッシの『ノー・ディレクション・ホーム』に多大な刺激をうけているのだろうということ。
「世代の唄」がとりわけ低声で語られる季節がふたたび巡り来たったような。
2007年問題の先頭を切ってシニアに突入した身として、いっそう強く感じるのだろうか。
『ダイハード4.0』なんかでも、ブルース・ウィリスがクリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルの講釈をして若者に馬鹿にされるシーンがあったりした。
まあ、クリームやレッド・ツェッペリンの復活を目にしてどんな感傷にひたるかは、それぞれの勝手だけれど。
とまれ、『ノーカントリー』を来年三月に映画館で観るなら、堂々のシニア料金で入ることができる。
原タイトルはずばり『老人の生きる国はない』だった。
トミー・リー・ジョーンズは当たり役すぎて……。缶コーヒーのCMのロング・ヴァージョンみたいなところもあり。
殺し屋ハビエル・バルデムは、『夜になるまえに』のレイナルド・アレナス役があまりに強烈だったせいもあって、今回はムニャムニャムニャ。
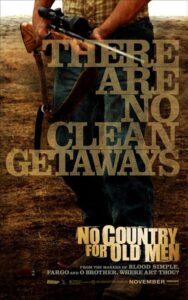
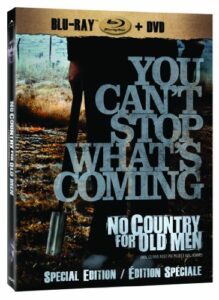
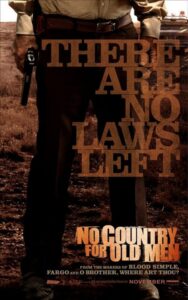
原タイトルはずばり『老人の生きる国はない』だった。
トミー・リー・ジョーンズは当たり役すぎて……。缶コーヒーのCMのロング・ヴァージョンみたいなところもあり。
殺し屋ハビエル・バルデムは、『夜になるまえに』のレイナルド・アレナス役があまりに強烈だったせいもあって、今回はムニャムニャムニャ。
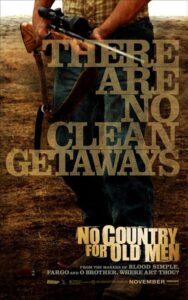
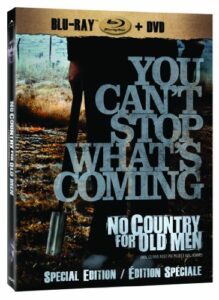
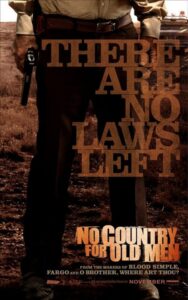
それにしても、『ファーゴ』でピーター・ストーメアがスティーヴ・ブシェミを「解体」しちまうシーンが思い出されてくる。