ホームページ更新日記2003.04.01 より
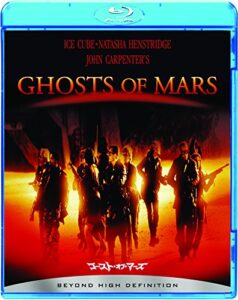
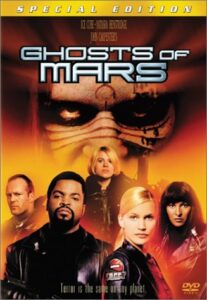
ジョン・カーペンターの『ゴースト・オブ・マーズ』は、想像を絶して、凄まじいばかりの幼稚なアホ映画であった。
まず、どうして舞台が火星植民地にとられているのか、最後までわからない。作り手は納得のいく答えをストーリーのなかに用意していない。とはいえ、これは「火星にするしかなかったんだろうな」となんとなく了解できることではある。
なぜなら――話があまりにタリラリラ~ンすぎるので、背景が地球の某所ではいろいろ具合のよろしくない点が百出したんだろう。
火星じゃなきゃ成り立たない話だ。すべてマイナスの意味合いにおいて。
つまりこれは、粗悪なアナクロニズムを作者と共有しなければ観てられないたぐいの恐るべき映画なのだ。
50年代のB級SFフィルムの世界に彷徨いこんだようなもの。居心地悪くならなければおかしい。
観客が50年代映画の世界にタイムスリップしたのではないと信じられるとすれば、多少とも特殊効果の映像にふれることができるシーンにおいてのみだろう。
たしかにテクノロジーの方面なら、人類は退歩していない。格段の進歩がみられる。
話はこういうものだ。
火星植民地のある街に凶悪犯を護送するために警官の一隊が送りこまれる。
凶悪犯にアイス・キューブ、警官隊の隊長にパム・グリアー、副長にナターシャ・ヘンストリッジ。
列車を交通手段とする辺境の、炭坑によって栄えている街――という設定も、いかにも西部劇スタイルを流用した安物のSFそのもの。街は火星人に乗っ取られていて、隊長はまっさきに戦死、副長が凶悪犯とその一党と協力して圧倒的多数の敵の攻撃に立ち向かう。
展開が定石通りのところは、まあ我慢するとしても……。


それにしても、同じエイリアン侵略テーマをあつかったスティーヴン・キングの新作『ドリームキャッチャー』の怒濤の迫力と比べて、どうにも薄っぺらいのには閉口する。
ステキンと『ハロウィン』のカーペンターでは格がちがうといえばそれまでだが。
火星人は一種の精神寄生体。宿主の肉体を借りて、ウンカのように攻めてくるというパターン。
このルールでくるなら、寄生の様態をあの手この手で見せてじょじょに恐怖を高めていくという演出がそもそも求められるはずだ。とくに前半はそれが勝負になる。
ところがこの盛り上げがなんともかんとも拙劣で苛々させられる。
カーペンターってこんなに下手クソだったっけ。
ストーリーは何の華麗さも技巧もなく、後半、善玉VS悪玉のドンパチという単純激突アクションになってしまうのだ。
この集団戦闘シーンにしても、もう少しなんとかならないのかね。もたもたとシンキくさい。
数だけは多いが原始的な武器しか持っていない敵と、劣勢小人数でも大量殺戮用の火器で対抗する正義の側。
この芸のない単純さ。
これはちょうど、50年ばかり昔に量産された西部劇映画の陳腐で使い古された図式の焼き直しにすぎないではないか。
インディアンならぬ火星人たちは次から次へとバタバタと射的のマトになって倒されていく。
この恐るべきワンパターン!
いやでも既視感が訪れてくる。
アメリカが介入したソマリア戦争を題材にした『ブラックホーク・ダウン』は、カルドーのいう「新しい戦争」の局面を垣間見せてくれたが、基本的なドラマは「騎兵隊VSインディアン」の戦闘映画だった。
しかし『ゴースト・オブ・マーズ』の場合は、単純素朴な焼き直しでしかないのだ。
――こりゃ、地球の某所の話にしたらいろいろと不都合が生じるだろう。
この映画のロケ地はニューメキシコ州の先住民居留区の鉱山だという。なんともはや皮肉なことだ。
作り手たちはことの皮肉に思い当たらなかったらしい。
周知のごとく「インディアン標的活劇」は、ある時代に特有の産物であり、それらはジョン・フォードの名作であれ、その他ひとからげにされる駄作群であれ、1970年前後の反省の時期をくぐって一掃された(フォードも反省的な作品を残した)。
同じものは二度とつくれない。
しかしまあ、SFのパッケージをほどこせば、つくれないこともない。
――と作り手は思ったのだろう。
他ならぬネイティヴ・アメリカンのリザベーションをロケ地に選んで、どんな霊感にとらえられたものやら。
それにしても、この映画のアホさかげんは、ここにとどまらない。
ラスト近く、危地を脱した騎兵隊は、違った、海兵隊は、また違った、地球防衛隊は、そのまま逃げるのではなく、人員が半数以下になっているにもかかわらず、もう一度、敵部隊の中枢に逆襲のためにもどることを決意する。
司令官(副長)は決意を隊員に告げる。
「この土地を支配するのは奴らなのか、われわれなのか。はっきりさせる必要がある。是非ともそうしなければならない」と。
どこかで聞いたセリフではないか。
安物の西部劇ではおなじみのセリフ。
既視感? いや、ちがう。
これは……これは、現実世界において、このところいやになるほど聞かされたセリフではないか。
サダムの大量破壊兵器に屈するのか。それとも自由と民主主義のために立ち上がるのか。
はっきりさせる必要がある。
決断をくだすのはきみだ。
とすれば、できそこないのSFアクション映画の絶望的なアナクロニズムは、あながち
作り手の救いがたいアホさを映しているのみではないのだ。
いや、まったく正反対だったりして……。
彼らの嗅覚は、まさしく現代のアメリカ帝国のルサンチマンの一部に、正確に対応しているのかもしれない。
ブッシュはたんなるアホ大統領ではない。最強帝国の戦略を発信するマシーンのメカニズムの一つなのだ。
テクノロジーは飛躍的に進歩したが、敵と己れの正義を分かつ叡知に関しては、致命的なほどの退歩をみせている。
現代世界の意識は、先住民居住区(国内植民地)をロケ地にした火星植民地映画にゾッとするほど正確に反映してしまったのかもしれない。
そして、「日米韓軍事同盟」下にあって、この国の支配層がとりうる選択肢も、それがどれほど弄劣な現われをみせようとも、自ずと限られているだろう。
スーパー帝国による統合軸に翼賛するために、各国家もまたそれぞれ国家主義への傾斜を深めていく。グローバリゼーションの時代、われわれの抵抗の根拠はますます困難になっていく。
この十数年の喪われた歳月の意味を問わねばならないと、痛切に思う。